2004年、新卒で入社した鈴木 隆文。アプリ・インフラの両方で、要件定義から運用保守までの全工程を経験し、幅広いスキルを身につけてきました。現在は開発推進室で生成AIの全社での利活用を推進し、開発者がより働きやすい環境を作る役割を担う鈴木に、これまで積み重ねてきたキャリアや、今後の目標について聞きました。
▲開発推進室の同僚との仕事風景(鈴木は写真右)
現在、鈴木が所属する開発推進室では、主に“開発の高度化”に取り組んでいます。
鈴木:「私は“開発の高度化”の中で、開発プロセスやツールなど、開発者が快適に働ける環境を整えていくことをメインに活動しています。“開発の高度化”とは、エンジニアが働きやすいと感じる環境や組織文化を向上させていくことで業務の質を高めるということを指しており、その一環として生成AIの利活用の推進に取り組んでいます。」
生成AIをうまく活用することで、エンジニアがより開発に専念できるようになると鈴木は言います。
鈴木:「例えば開発中にエラーが起きたとき、エラーメッセージをそのまま投入するだけでそのエラーの原因と対策を教えてくれるので、問題解決までの時間をかなり短縮できるんです。また、書きたいコードを自動提案してくれたりもします。このように生成AIを活用することで、本来頭を使うべきことに集中でき、品質向上や工数削減を図れます。削減できた時間を使って、新しい技術を学んだり、案件外の活動に参加したりする時間を取れるようになるなど、新たな価値を生み出せることも、開発の高度化を進めている一つの背景です。」
開発推進室での業務のかたわら、社内外での活動にも積極的に参加しています。
鈴木:「2015年から、日本ITストラテジスト協会(JISTA)に参加しています。これは、情報処理技術者試験の中のITストラテジスト試験に合格した、もしくは合格を目指す人が集まる技術コミュニティです。月1回ほど集まって、組織戦略に沿ったIT戦略をいかに考えていくかなどを話し合っています。
クレスコ社内では、2020年からクラウド技術コミュニティ、2021年からアジャイル技術コミュニティに参加しています。現在はアジャイルの方にメインで入っていて、アジャイル開発に関するエンジニア育成や案件支援などを行っています。」

▲学生時代、合気道部の同期と(鈴木は写真左)
長年にわたりシステム開発の世界で活躍してきた鈴木ですが、大学での専攻は意外にも生物工学でした。
鈴木:「元々DNAに興味があったため、大学・大学院ともに生物工学について学んできました。プログラミングに関心を持ったのは4年生の卒業研究の時。データマイニングを使ってトマトの生産量を予測するという研究でした。それまでは基本座学メインだったので、プログラミングだと手を動かすことが新鮮に感じられ楽しかったのと、データ処理にエクセルを使っていた際すごく時間がかかっていたのが、プログラミングを使ったことで劇的に時間短縮できてとても感動したことを覚えています。」
この体験をきっかけに、大学院では植物生産関連のシステム開発について研究するようになった鈴木。就職活動では、狙いをIT業界に絞りました。
鈴木:「いくつかのシステム開発会社を受けた中でクレスコを選んだのは、人材育成に最も力を入れている会社だと思ったからです。当時はまだ自分の技術力がどこまで通用するか不明瞭だったので、人材育成に強いという点は非常に魅力的でした。」
入社後は、保険・金融業界向けの基幹システムや小売業向けECサイトなどの開発に携わってきました。
鈴木:「最も長く携わった保険会社向けの基幹システムでは、アプリケーション開発における要件定義から設計、開発、テスト及び運用保守まで全ての工程を経験できました。これが私にとって、アプリ開発の土台になったと思います。
別のクラウド開発案件では、逆にアプリから離れてインフラだけをやっていました。こちらも要件定義から運用保守まで、全工程を経験することができました。アプリケーション開発とインフラ開発の両方で、全工程を経験したという点が、私のキャリアの特徴だと思います。」
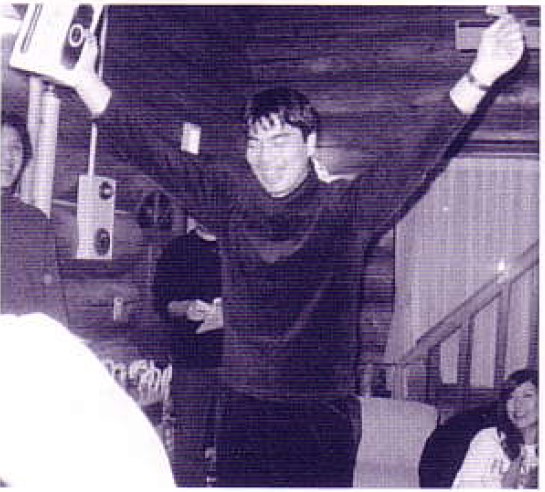
▲若手時代、社員旅行にてゲーム機をゲットした鈴木(写真中央)
2020年、鈴木はITアーキテクトとして、コネクティッドカー向けのクラウドシステム開発案件に参画します。
鈴木:「これまで参画したいくつかの案件の中でも、最も思い出深い案件の一つです。というのも、私にとって初めてのアジャイル開発案件だったからです。アジャイル自体は以前から少しずつ勉強はしていましたが、実務で携わるのはこの時が初めてでした。
短いサイクルで開発していくのがアジャイルの特徴ですが、お客さまと密にコミュニケーションを取りながら開発を進めていくという点が、非常に面白いと感じました。」
アジャイル開発という点以外に、この案件にはもう二つ大きな特徴がありました。
鈴木:「一つめは、1人のエンジニアがアプリとインフラの双方を担当することが求められていた点です。先ほどお話ししたように、私にはアプリをやっていた時期とインフラをやっていた時期がありましたが、私にとってこの案件は、今までやってきたことの集大成のように感じました。
もう一つは、月イチくらいのペースで、Amazon Timestream(※)やAWS IoT Core(※)など、新しい技術を取り入れていった点です。私が経験してきた他の案件では、新技術の導入はせいぜい年に一つ二つでしたが、この案件はとにかく成長速度が早かったと思います。
正直、キャッチアップするのが大変でしたが、ヒイヒイ言いながらも取り込むことができていたので、それだけ自分にも応用力が身についてきたと実感することができました。」
新しい技術に出会うたび、鈴木はそれらとまっすぐ向き合い、自分のものにしてきました。
鈴木:「あの頃は、ドキュメントを見て、サンプルを動かして、動きを確認する、という作業を、愚直にやり続けていたように思います。書籍や公式ドキュメント、誰かが書いたブログなど、いろいろ読み漁っては試すうちに、使える技術が増えていきました。」
※Amazon Timestream:フルマネージド型の専用時系列データベースエンジンを提供するサービス
※AWS IoT Core:フルマネージド型のIoTデバイス接続サービス

▲開発推進室 鈴木 隆文(スズキ タカフミ)
ITの世界に足を踏み入れて20年。鈴木には仕事において心がけていることがあります。
鈴木:「自分のタスクを、極力自分自身でコントロールできる状態にするように意識しています。私は突発的なことにうまく対処できるほうではないと自覚しているので、いつ何をするかを計画通りに進めて、常に業務をコントロールできる状態を心がけています。それはもちろん一緒に仕事をする仲間に対しても同じで、何かを依頼する時は極力相手のスケジュールを乱さないように気を付けています。
また、仕事を依頼するときも依頼されるときも、どういう状態になればその仕事が終わりと呼べるのかを、お互いにきちんとすり合わせることを心がけています。経験上、ここをおざなりにすると、案件の進行の妨げになる可能性が高いと実感しているからです。」
現在の目標は、生成AIの利活用をより加速させ、会社全体の生産性を高めることだと言います。
鈴木:「1人のエンジニアとしては、以前のように現場で開発業務に携わりたいという思いも少なからずあります。ですが今はバックオフィスのメンバーとして、自分の知見やノウハウを全社に広め、現場のエンジニアを支援することに全力で取り組んでいます。
先日、実際に生成AIを導入しているチームの方と話す機会があり、『すごく便利になった』『業務の生産性が上がった』という声をもらうことができ、とても励みになりました。生成AI自体も新しいものがどんどん生まれてきていますし、活用方法もこれから広がっていくことは間違いないので、今以上に活用してもらえると嬉しいですね。」
ITエンジニアとして、これまでに数々の新技術に出会ってきた鈴木にとっても、近年の技術革新のスピード感は、過去に経験したことがないほどだと言います。激しい開発競争の中、現場のエンジニアたちへのサポートをより強固なものにするため、鈴木の挑戦はこれからも続きます。
※ 記載内容は2024年11月時点のものです。
